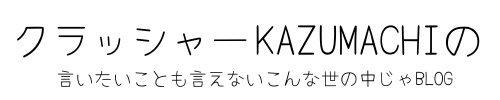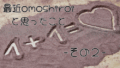がっつり就職の前にやりたいことがあんねん。
どうも。みなさん。クラッシャーでございます。
最近、友達と「ミッキー17」という映画を見に行ってきました。
ただ、映画に行く数日前に、カバーソングを作っていたので、若干の少しだけ左耳が痛い状態だったのですが、「せっかく誘ってもらったし行きたいなあ、まあ大丈夫っしょ!」と思いなが映画館へ向かいました。
映画はDolby Atomosの立体音響システムのバージョンで鑑賞していたのですが、映画の最後の方で、大量のエイリアンたちが一斉に叫ぶシーンがあって、そいつらとDolby Atomosの立体音響のせいで、もともとちょっとだけ痛かった左耳がさらに痛くなりました。
なので、これからもし見に行く人がいたら、ぜひ耳栓を持って行ったほうがいいです。
というわけでございまして、私KAZUMACHI、先日ある歌のオーディションを受けてきました。
場所は渋谷です。

渋谷ヒカリエ。でっけぇ!

ヒカリエの隣にあったビル。なんかヒカリエ近くのビル全部でっけぇ!すっげぇ!

そして、ヒカリエと渋谷駅の連絡通路の上も通れるようになるっぽい。すっげぇ!
年齢不問の誰でも受けれるやつです。
がっつり就職の前に、プロの人に自分の歌を一回でいいから聞いてみて欲しいなと思って、勇気を出して受けに行ってきました。
自分としては、「これなら人前で歌っても大丈夫そう」とか、自分でもいいかもと思えるような歌を、少しづつですが歌えるようになってきてる気がしてたので、プロの人がどう僕の歌を評価するのかを知りたかったんです。
まあとりあえず、たぶん落ちたというか、受かっても次に進めないことが確定したので、オーディション自体はもう終わったは終わったんですけど、でも自分の歌をある程度は評価してもらえたので、割と満足しました。
なので、一応選考状況とか、オーディションの詳細についてはブログとかでは言えない決まりっぽいので割愛するんですが、でもとりあえず今回のオーディションは受けてよかったです。
歌に対して、またひとつ考え方が変わりました。
今までは、その曲が好きだからカバーするとか、自分がなんとなくいいなと思えるような声で歌うとかの歌の技術的な部分にこだわっていたことが多く、そんな感じでただ楽しく歌が歌えてたらいいなと思っていましたが、それだけだとなんか足りないかもって気づいて、もっと「なんでその歌を歌うのか」とか、その歌を歌う目的だったり、意味みたいなものが自分の中で明確になっていないと、たとえその歌をうまく歌えたとしても、芯のない歌になっちゃうなって思うようになりました。
だから家で練習しているときに、その芯がある状態で歌を歌えたときには、自然とその歌が自分にfitして歌えているような感覚になる時があります。
まあ、自分の勘違いなのかもしれんけど。
ある歌を作った人は、何か伝えたいことがあるからその曲を作っているので、なんでその歌を歌うのかが、当たり前ですけど初めから明確です。
だから、誰かアーティストの曲をカバーするときには、それを作った人とは毎回逆の作業を本当はしていなきゃいけなかったなと。。。
なので、もう今は「なんでその歌を歌うのか」とか、「なんでここはこういう歌詞なのか」などなどを、ちゃんとしっかり自分なりに咀嚼してからじゃないと、その歌がなんか歌えなくなりました。(歌えるけど、ただの発声練習とか楽しみとしての歌にしかならない感じがしてます。まあ別にそれでもいいんだけどもね。)
そして、これらに気がつけたのは全部、オーディションの前にYouTubeで死ぬほど見た、ボイストレーナー菅井秀憲先生のレッスン動画のおかげです!
ありがとう。。。菅井先生。。。
ちなみに、「道重さゆみ vs 菅井先生」という動画があるんですが、2人の掛け合いがプロで面白いのでおすすめです。
というわけで、今後がっつり就職をした後も今まで通り、カバーソングをネットに上げたりとか、自分で作曲してみたりとか、そんな感じで自分なりにいいと思える作品を作りながら、ゆるーくながーく歌を楽しみながら生きていきたいと思いマッスル。
また、さらに余談ですが、僕はカナダにいたときにもCMのオーディションを受けたことがあったので、今回のオーディションは実は人生で2回目でした。
そのCMのオーデションでは、すごい短いセリフだったんですがセリフがありました。しかし、そのセリフがなんか覚えられなくて、うろ覚えで行ったら、ただでさえ大根役者なのに、緊張でさらにセリフが出てこなくなって、その様子を見たそのCMの監督が困惑していました。
まあ当然落ちました。
というわけで、あとはどこかの出版社に、「奴隷力」とかの書きたい本の企画書を作って持ち込みしてみようかなとも計画しているので、それらについても、進展があったらまた今後このブログで紹介したいと思います。
では、今回は以上です!
おわり